電子カルテと紙カルテを徹底比較!

最近、医療機関などで電子カルテが導入されているのを目にすることも多いと思います。
また、医療のレベルを向上させるために、厚生労働省では電子カルテを標準装備することで診療所や病院に設置しようという施策を行っています。
紙カルテと比較して、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
電子カルテとは?

電子カルテとは、診療記録などカルテの情報を電子化したシステムのことをいいます。
従来のように紙を使うことはありません。
紙カルテと違って、どこにいてもパソコンやタブレット端末などがあれば患者のカルテを簡単に引き出すことができます。
また、カルテに記載されている情報をただ電子化するだけではなく、医療機関の業務全体を効率化する機能が搭載されているものもあります。
会計業務に使われることもありますし、検査結果を書き入れることも簡単です。
まだ全国どこの医療機関でも使用されているというほどではありませんが、現在徐々に普及率が上がってきており今後もより一層普及していくことが期待されています。
電子カルテのメリット
電子カルテには、下記のようにさまざまなメリットがあります。
すぐに情報を引き出せる
紙媒体の場合、名前順や診療日順など、付箋などで情報を整理して保管します。
しかし、探す手間がかかってしまうため作業効率が低くなることから、時間内に多くの患者さんを診療できないことがあります。
また、紙媒体の場合はコピーや持ち出しなど、物理的な情報漏えいの可能性があるため、関係者でしか開けられないように保管するなど、場所や管理費用が発生します。
電子カルテなら検索するだけで簡単に必要な情報を引き出すことができ、すぐに編集を行うことが可能です。
また、クラウド型なら電子カルテメーカーのサーバー上に、オンプレミス型なら自社サーバーに患者さんの情報を保管するため、最低限の場所で保管できる点もメリットです。
視認性が高い
人が書いた文字だとクセがあるので、場合によっては読みにくいことも少なくありません。
電子カルテはパソコン内のフォントで入力するため、視認性が高い状態で情報を記載できます。
特に、クラークを導入している診療所では、さまざまな人がカルテに書き込むため、高い視認性が求められます。
誰が見ても見やすい情報が表示される点も、電子カルテを導入するメリットといえます。
電子カルテの注意点

電子カルテを導入することで、先述の通りさまざまなメリットを得られる一方、使用時には下記のようにいくつかの注意点があります。
停電時に使用できない
電子カルテは院内の電気を利用して情報を書き込んだり探したりするため、停電時など災害が発生した場合に利用できないリスクがあります。
診療所のなかには自家発電装置を備えている施設もありますが、災害時には断線や接続不良、システムダウンの可能性があります。
そのため、電子カルテを導入する際、メーカーに停電時の対処法などを事前に確認しておくだけではなく、万が一に備えて紙媒体でも診療できる仕組みも準備しておくと安心です。
セキュリティ対策
電子カルテは院内に通っているネットワークを利用するため、コンピュータウィルスやマルウェアの被害にさらされる危険性があります。
特に、クラウド型は院外のサーバーに情報が保存されているため、悪質なサイトなどを閲覧してしまうとそこからウィルスが侵入し、患者さんや院内の情報が抜き取られてしまうことがあります。
また、オンプレミス型についてもUSBメモリなどを使って大量のデータを院外に持ち出されることも考えられます。
セキュリティ対策を万全にし、情報漏えいを防ぐためにはログの管理やアクセス制限など、セキュリティを厳重にしましょう。
初期費用と維持費が必要
クラウド型、オンプレミス型問わず、電子カルテを導入する際は機器の料金やシステム料などの初期費用が必要です。
また、導入後も保守費用や光熱費など、さまざまなランニングコストが発生します。
このように、電子カルテを導入、使用する際にはさまざまな費用が必要ですが、現在ではIT機器の導入に関する補助金や助成金が利用できます。
そのため、電子カルテの導入を検討している方はメーカーや補助金・助成金の窓口担当に、いくら程度補助を受けられるのかを聞いてみることをおすすめします。
紙カルテとは?

紙カルテは古くから診療所や病院などで使われており、ペンで記載する紙媒体のカルテです。
紙で管理するメリットには、文章力や語彙力、記憶力の向上といったメリットがあるといわれているため、ベテランや個人経営の医療機関などに勤務する医師のなかには、現在でも紙カルテを使用する方がいらっしゃいます。
紙カルテのメリット
こちらでは、紙カルテのメリットをご紹介します。
低コストで運用できる
紙媒体であれば、電子カルテのように導入時に多額の費用がかかるということはありません。
先述の通り、電子カルテを導入する際は初期費用が必要なだけではなく、サポートを受けるためにはランニングコストを支払う必要があります。
特に、診療所の開業を検討している方にとって、高額な初期費用は大きな負担になるものです。
そのため、ほかの設備を充実させるために、電子カルテを導入せず紙カルテを使用する医師も多くいらっしゃいます。
災害に強い
紙カルテは地震や停電といった災害時でも視認できるというメリットもあります。
電子カルテの場合、災害が起きると停電が発生して電気が使用できなくなることがあります。
しかし、紙媒体は電気を使用せずに視認できるため、急患でも柔軟に対応できることから、現在でも紙カルテを使用している医療機関も存在します。
手軽にメモを記載できる
電子カルテの場合、書き込める場所が限られているフォーマットが搭載されていることがあります。
そのような場合、患者さんとの会話のなかで得た情報を書き込む場所に困る方もいらっしゃいます。
紙カルテは電子カルテよりも記載する場所の自由度が高く、すぐに情報を書き込めるため、利便性が高いと感じる方も多いものです。
しかし、現在ではペンタブなどを使用して、紙カルテのように記載できる電子カルテも提供されているため、電子カルテの利便性も向上していると言えるでしょう。
紙カルテの注意点
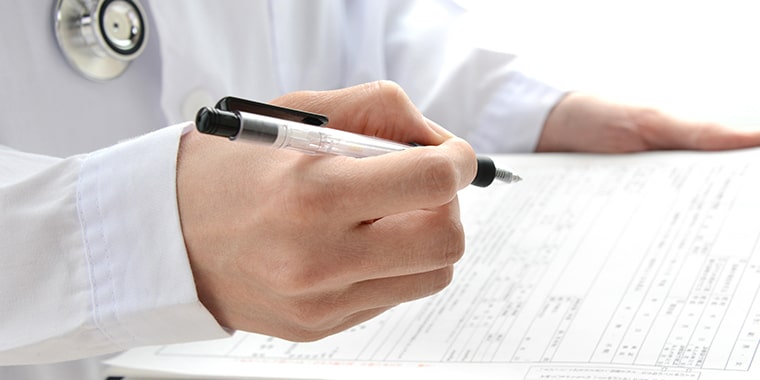
紙カルテにもさまざまなメリットがある一方、下記のような注意点があります。
複数人で同時に視認・記載がしにくい
紙カルテは1人の患者に対して1枚・1冊で管理するため、複数人で同時に視認、記載がしにくい点は、電子カルテよりも業務効率が低くなってしまうと言えます。
たとえば、クラークは医師に代わってカルテに診療情報を記載しますが、診療中に医師の前に置かれたカルテに記載すると邪魔になってしまいます。
そのため、誰かが使用している時にはカルテを閲覧することができないという点には注意が必要です。
保管場所が必要
紙カルテは物理的に存在するため、保管場所が必要です。
患者さんの数が少ない場合は少ないスペースで保管できますが、数年間診療すると紙カルテの量は増加していき、多くのスペースが必要になります。
また、紙カルテの量が増えるほど患者さんの情報を探すのに時間がかかるため、徐々に効率が下がってしまう可能性があります。
そのため、紙カルテで診療する際は、カルテの保管場所を検討しなければならない点も注意が必要です。
情報を探しにくい
紙カルテに記載する人によっては、書き方などが統一されていないことから、視認性が下がってしまうため、情報を探しにくくなることがあります。
カルテには患者さんの基本情報や症状、現病歴など、さまざまな情報を記載しますが、そのなかから当日の診療に必要な情報を探すのは、時間がかかるものです。
特に、長い間通院している患者さんの場合、紙カルテが何枚にも及ぶため、膨大な情報から必要なものを抜き取るのは大きな手間になるでしょう。
電子カルテの場合は検索窓などで調べたい情報を抽出できるため、業務効率は紙カルテと比べて高いといえます。
電子カルテでよくある疑問

電子カルテを導入する際、「紙カルテから電子カルテへの移行方法が分からない」「保存期間はどれくらい?」といったご質問を多くいただきます。
こちらでは、それぞれの質問への回答をご紹介します。
紙カルテから電子カルテへの移行方法
紙カルテを使用していた診療所が電子カルテに移行する際、下記の手順で行われます。
- 電子カルテを選ぶ
- 操作方法を学ぶ
- 紙カルテを電子カルテに取り込む
紙カルテを取り込む際、スキャナーを使用することが多いです。
また、膨大な紙カルテを自分でスキャンすると、多くの時間を費やしてしまうため、メーカーが代行してくれることがあります。
取り込んだ紙カルテのデータは電子カルテと同様に、参照したりさまざまな情報を記載したりできます。
保存期間
電子カルテの保存期間は、厚生労働省によって5年と定められています。
保存期間の起点は診療が完了した日からカウントします。
こちらの期間は紙カルテと同様で、なかには3年といわれることがありますが、保存期間が3年の書類は帳簿や領収書などです。
比較結果

電子カルテは紙カルテに比べて、患者の情報が引き出しやすいという特徴があります。
検索すればすぐに見つかりますし、編集なども簡単に行うことができます。
一人の人が閲覧していても、他の場所で別の人が閲覧するといったこともできます。
それにより業務をスムーズに進められることにつながります。
電子媒体だと字が読みやすいというメリットもあるので、複数の医師や看護師が診療に携わる業務にこそ向いています。
初期投資にかかる費用は紙カルテに比べて高くなりますが、業務が効率化されることで人件費が抑えられるなど、それを上回る効果を期待できます。
保管スペースも省くことができるでしょう。
ただし、高度なセキュリティ対策を行う必要はあります。
おわりに
電子カルテにも紙カルテにも様々なメリットとデメリットがあります。
どちらか一方に頼るのではなく、それぞれの強みを生かした使用方法をすることにより、より一層業務の効率化がすすめられるのではないでしょうか。
株式会社ユヤマ
最新記事 by 株式会社ユヤマ (全て見る)
- 医療DXの基本とは?今すぐ知っておきたい具体例とメリット - 2026年2月4日
- 【電子カルテ導入事例:整形外科編】開業3年で累計18万人。1日平均280人の診療を支えるBrainBox【インタビュー動画のご紹介】 - 2026年1月28日
- 分包機の操作やお手入れの「困った」をすぐに解決!「動画HELP」活用のススメ - 2026年1月20日







 電子カルテ導入のメリット・デメリットとは?クリニックへの導入で失敗しないための選び方も解説
電子カルテ導入のメリット・デメリットとは?クリニックへの導入で失敗しないための選び方も解説 電子カルテのオーダリングとは
電子カルテのオーダリングとは 知ってる?電子カルテの導入で医療現場はどう変わるのか
知ってる?電子カルテの導入で医療現場はどう変わるのか 医療のICT化とは?電子カルテを含むICTを理解しよう
医療のICT化とは?電子カルテを含むICTを理解しよう クラウド型電子カルテが今後の医療にかかせない訳とは
クラウド型電子カルテが今後の医療にかかせない訳とは 電子カルテとレセコンについて 連携するメリットもご紹介
電子カルテとレセコンについて 連携するメリットもご紹介