電子カルテを導入する前に気を付けたいデメリット
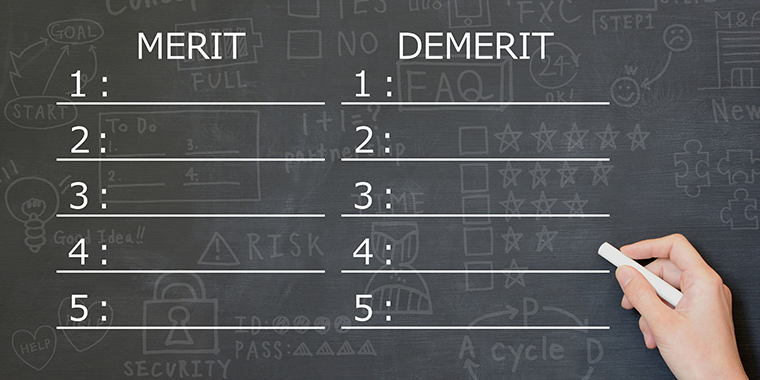
医療機関では欠かすことの出来ないものとしてカルテがあります。
医療の進歩にともない業務も煩雑化していましたが、カルテを電子化することで、作業効率をアップできるようになりました。
便利な方法ですが、導入を検討する前に知っておきたいポイントを紹介していきます。
紙と電子カルテの違い
医師が診療時に、患者を診察した内容を紙に記載していたのが紙カルテであり、パソコン上に入力するのが電子カルテです。
昔はすべて手書きでカルテを記載していましたが、電子カルテの登場により作業が効率化され便利なものになっています。
情報をデータ化することで、必要に応じて編集や検索などの他に、紹介状などの書類作成にも一役買っています。
また、紙カルテの場合は保管場所が必要で管理をする手間もかかります。
その点では電子カルテなら膨大なデータを目に見えない領域に保存できるので、同じカルテでもスペックの高い電子カルテの方に軍配があがるといったところです。
特に1日に多くの患者が訪れる医療機関であれば、電子カルテの導入は不可欠であるといってもよいでしょう。
経費への考慮が必要

業務の効率化の点で直ぐにでも導入を検討したいところですが、導入前にはメリットやデメリットを知っておく必要があります。
特に気を付けたい点として、まず電子カルテの導入には、それなりに経費がかかってしまいます。
また、初期費用だけではなく、毎月の維持にかかるコストも考慮しなければなりません。
事務をする上で便利な反面、経費がかかることは必然なので、施設にとってメリットがあるのか十分に熟考するべきです。
ただ、ランニングコストなど、長い目で見ればメリットの方が高いことがわかります。
最近ではベンチャー企業の参入で、費用を抑えた商品もどんどん開発されているので、その辺りの情報も集めたほうがよいでしょう。
選択肢が増えるというだけでも、導入しやすくなります。
システムに慣れるまで時間が必要
これもデメリットといえる一面ではありますが、導入後にデジタルな対応ができるまでには、ある程度の時間が必要となります。
今までアナログに慣れていたところに急なデジタルでは、どうしても対応できるまでに時間がかかるというものです。
いくら効率がよくなるとはいっても、操作方法を覚えなければなりません。
日頃から機械に精通していれば困ることもないのでしょうが、不慣れな人にとっては死活問題です。
また、新しく入ってきた新人のスタッフにも指導しなければならないので、初めのうちは逆に時間を取られることになってしまいます。
ですが、一度ルーティンが組まれていけば、時間の短縮に繋がっていきます。
スタッフとしても効率化されていくのはメリットですから、最初の内はこれも必要なコストとして捉えましょう。
停電の可能性

電子カルテの利用において、一番危険なのが停電です。
普段気をつけていたとしても、こればかりは100%防ぐことは不可能だといえます。
電気を通さなければ使用できないのがシステムですから、当然停電が起きてしまえば一発でアウトです。
またその際にバグなどの不具合があれば大変なことになります。
データの破損はまだいい方ですが、不正にアクセスされたり、データの改ざんや情報漏洩が起こったりと様々な最悪の事態が想定されます。
その為には万が一の時に困ることのないように、常に保守点検やバックアップ体制を取るなど、あらゆる手を打っておくことが大事です。また厚生労働省ガイドラインによって医療機関は医療情報システムの「運用管理規定」を定め、遵守することが義務づけられています。
おわりに
大量のデータを扱う上でカルテを電子化することは、メリットが多いのですが、同時にデメリットも伴います。
費用の面からリスク回避まで、あらかじめ万全の体制を整えておくことが、システム導入に欠かせないでしょう。
株式会社ユヤマ
最新記事 by 株式会社ユヤマ (全て見る)
- イギリスの薬局事情(前編) - 2024年4月16日
- 診療所経営で開業医が支払う税金と経費として計上できる費用をご紹介 - 2024年3月28日
- 錠剤分包機への薬品の誤充填を防ぐ取り組み - 2024年3月18日







 電子カルテと紙カルテを徹底比較!
電子カルテと紙カルテを徹底比較! 電子カルテのクラウド型とオンプレミス型の違いとは?
電子カルテのクラウド型とオンプレミス型の違いとは? 電子カルテの導入効果を得るための工夫とは?
電子カルテの導入効果を得るための工夫とは? クラウド型の電子カルテを選ぶ比較ポイント
クラウド型の電子カルテを選ぶ比較ポイント 電子カルテの歴史とは?過去と現在から見る今後の電子カルテ
電子カルテの歴史とは?過去と現在から見る今後の電子カルテ 今更聞けない!電子カルテの基礎知識と可能性
今更聞けない!電子カルテの基礎知識と可能性